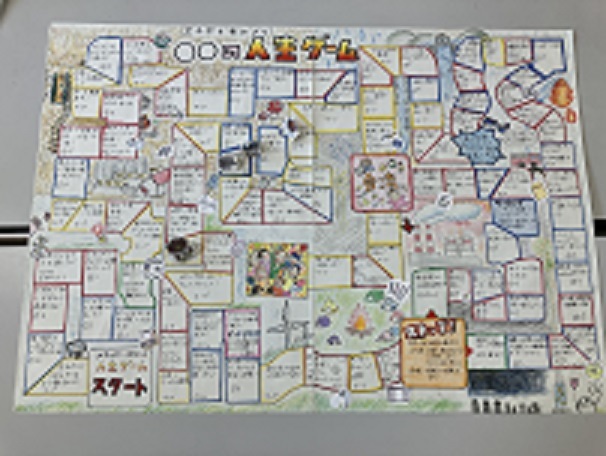9年 紫翔祭に向けて(大縄跳び)






紫翔祭に向けて、9年生は伝統の種目である大縄跳びの練習に励んでいます。大縄跳びは女子90秒、男子90秒、そして男女混合120秒の合計回数を競う競技で、毎年最も熱く盛り上がる場面のひとつです。限られた時間で記録を伸ばすために、生徒たちは朝の授業が始まる前や昼休みを使い、息を合わせて繰り返し挑戦しています。大縄を回す手に力を込める生徒、タイミングをとるために声を掛け合う生徒、失敗してもすぐに立ち直り再び挑戦する姿に、学年全体の団結とエネルギーが感じられます。また、特別支援学級であるD組の生徒たちも団旗や学級旗を手に応援し、仲間の頑張りを後押ししてくれています。練習の場には一体感と熱気があふれ、本番に向けて気持ちが一層高まっています。紫翔祭当日、9年生の全力と絆がどのような記録を生み出すのか、期待が膨らみます。